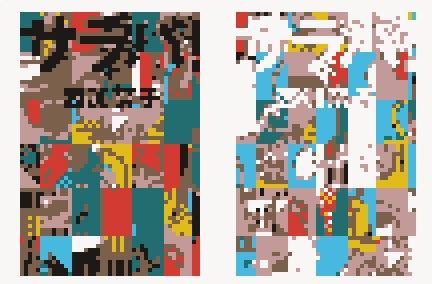
「感情を発露するのは、いつだって姉だったし、母だったし、とにかく僕以外の誰かだったのだ」
この一節を読んだとき、私は家族で過ごした全ての時間を思い出した。
私が生まれた時に、そこにはすでに"家族"があった。
"夫婦"のもとへ姉が生まれ、出来上がっていた"家族"の中に私が途中から参加したのだ。
自分は姉を見て育ったし、その分いい子ではなく「怒られないように心がける子」に育っていった。
もちろん親に叱られることも沢山あったが、親と"喧嘩"をするのはいつも姉だった。
自分の考えていることが、その外で起きていく数多のことに追いつかず、そのズレがどんどん溜まっていく感覚が幼い頃からあった。
その結果、昔の私は口数がどんどんと少なくなっていった。
私は自分が頭で考えていることを外へ翻訳することよりも、周りの言葉に反応する速度の方を上げることで、少しずつその摩擦は減っていったが、本書の主人公である歩は、その転機を持たずに大人になっていく。
彼はとにかくひたすら、外との摩擦を減らすことを念頭に生きるようになっていったのだ。
円滑に人と接するという信念は、自尊心を削り取ること機会を失い、彼の中の孤独なプライドを育てていく。
「私を見て!」という感情を発露して周りとぶつかり、問題を起こす姉 貴子のことを見てきた歩は、きっと「こうするべきではない」と自分に言い聞かせてきただろう。
それと同時に「僕を見て!」という感情を外に出す術を失い、自身の中で燻らせてしまったのだ。
この本は"そつなく"生きてきた主人公 歩が、自分を"自分の人生の主人公"にするまでの物語だ。
あらすじ
僕はこの世界に左足から登場した――。
圷歩は、父の海外赴任先であるイランの病院で生を受けた。
その後、父母、そして問題児の姉とともに、イラン革命のために帰国を余儀なくされた歩は、大阪での新生活を始める。
幼稚園、小学校で周囲にすぐに溶け込めた歩と違って姉は「ご神木」と呼ばれ、孤立を深めていった。そんな折り、父の新たな赴任先がエジプトに決まる。
https://www.shogakukan.co.jp/books/09406443
メイド付きの豪華なマンション住まい。初めてのピラミッド。
日本人学校に通うことになった歩は、ある日、ヤコブというエジプト人の少年と出会うことになる。
本書は文庫本にして「上」「中」「下」の3巻に渡る長編だ。
上巻は、主人公 圷歩(あくつあゆむ)の誕生から小学生まで。
中巻は、小学生から26歳まで。
下巻は、26歳から37歳まで。
彼の一人称視点でひたすらに人生が描写されていく。
歩はイランで生まれ、エジプトに引っ越しその先で親友ができる。
しかしその矢先、日本に帰ることになり、それ以降は日本で生活を送る。
幼年期、少年期、青年期を「家族」「学校」「社会」のスケールに展開していきながら、歩が育んでいく人間性とその遠回りな転機を描く。
すゝめ
本書の長さから、なかなか手を出しづらい本ではあると思う。
しかし、その分厚さから構えていたよりもずっと読みやすい文体でスイスイと読める作品だ。
何より、母の存在感が大きい家族だった、自分より溌剌な兄や姉がいる、周りに合わせる小器用さがあるといった人にとっては、他人事には思えないようなディティールで物事の描写が続くだろう。
主人公が幼年期に感じる「家族内での自分の立ち位置の安全さ」であったり、少年期に抱える「人気者になりたい訳ではないが、その横にいたい」という気持ち、青年期に育つ「自分はうまくやれているはずだ」というプライド。
そのどれもが人間らしく当たり前のものだろう。決して劇的な人生ではない。
決定的な出来事や、運命的な出会い、屈辱的な別れなどを通しても、彼はどこか他人事のように、あっさりと人生をくぐり抜けていく。
波風を立てずにいるための選択を続ける癖がついた彼は、自分の人生と向き合うことができるのか。
周りに巻き起こる"ただの人生"をいなしてきた歩が、"自分の人生"を一歩踏み出すまでの37年を是非見届けてほしい。

レビュー【ネタバレあり】
ここからは具体的なシーンなどに触れていきます。
作品をまだ見ていない方にはおすすめしません。
主人公 歩が決まって言われてきた「いつもそうだよね」「何考えてるのかわからない」「どうしたいのかはっきりして」という言葉は、ひどく暴力的に私の心を抉った。
問題を避けて、静観して、揉め事を起こさずにいることが悪いことなのか?
「自分がどうしたいか」よりも先に彼に浮かんだ疑問はこれだった。
情けない事に、痛いほどよくわかる。
前述した通り、私は"家族"のもとへ一番最後にやってきた。
そして親の転勤による引っ越しで、すでに出来上がった"友達"という関係の中に途中から混ざることが多かった。
コミュニティの中で生きていくには、常にすでにある場所を伺って、入る隙間を見つけてそっと忍び寄ることしかできなかった。
ふるさとと呼べる土地感覚は度重なる引っ越しや寮生活で薄れていき、精神的にも物理的にも自分の居場所というものにアイデンティティを置くことがほとんどなかった。
あくまで自分はお邪魔させていただいている。そんな感覚がずっと私にはあった。
問題を避けて、静観して、揉め事を起こさずにいることは、自分にとって自分の居場所を守る数少ない術だったのだ。
色々な事に対して引け目を感じ、0にすら届かないものにまみれている。
だからこそ、自分を慰めるためのプライドが育ち、他人の溌溂とした感情のアウトプットを僻んでしまう。
あんなに歩の周りに問題を巻き起こしていた姉 貴子が、数年越しに会うとすっかり悟ってしまっているのもリアリティを感じざるを得ない。
こっちは気を使って、息を潜めて、感情の嵐が過ぎ去るのを耐え忍んできたのに、感情を発露することに飽きた姉はすっかり「次のステージ」かのような顔をしているのだ。
そらあんたはスッキリしてるやろうに。
じゃあ僕はどうしたらいい。
歩はきっとそんなふうに思ったことだろう。
ただ、果たして姉が悪いのか?
きっと歩も感情を発露する術を身につけていれば、何も問題はなかった。
周りで起こる問題に対して一歩引く選択をとっていたのは、あくまで歩の意思だ。
そんな彼が手に入れた感情の発露は、文章を書く事だった。
旧友(ヤコブや須久)との思い出が、それを突き動かし彼を生かしていく。
思い出は自分の元へ立ち返ってくるものではない。
世界に散らばるそれを見つけ、そこへ向かって歩みを進めなければならない。
自分の思い出を自分で回収していくことで、自分の人生は自分の人生たり得るのだ。