コーラの味と、コーラ味は少し違う。
涙ぐましい企業努力によって、それらは具体的にどう違うかはほとんど言語化しづらいが、その二つは確かに少し違っている。
しかし、コーラ味はあくまで"コーラを再現した味"であり、その距離の近さに私たちも「これはコーラの味だね」と自ら寄り添いっている。
コーラっぽさを巧みに再現されたグミやキャンディに、私たちは元ネタたるコーラを彷彿して納得しているのだ。
「コーラ味」と言い張り、コーラっぽくなろうと励むその味を、偽物のコーラ風味を私たちは「コーラだね」と肯定している。
「〇〇味」「〇〇風味」「〇〇風」などと言われると、なんだか違和感なくその嘘を肯定したくなる。
なんだってあくまで"風味"な訳だ。それは偽物を肯定し、もう一つの本物に仕立て上げる優しい言葉だろう。
みかんっぽい味
こんなことが書かれたパッケージがあれば、なんだか不安になるだろう。
実際は「みかん風味」とさして変わらないというのに、なんだかめっぽう自信がなさそうに感じてしまう。
では逆にこう書かれているパッケージはどうだろう。
みかん
これはもうみかんその物じゃないとダメだ。"みかん"って言っちゃってる。
あの橙色の柑橘果実がゴロンとそのまま入っていて、やっと「確かにこれはみかんだ」となる。
いや、そもそもみかんに「みかん」と書かなくていい。
そんなもん見れば分かるわ。馬鹿にするな。
なぜみかんではないものに、「みかん味」だとか「みかん風味」などと書かないといけないのか?
それは他でもない。
それが「みかん」ではないからだ。

私たちは色々な偽物を許容して生きている。
タブレット端末とタッチペン。
これらが紙と鉛筆とは全然違う性質をしていることは皆が知っているだろう。
けれども、最近はタブレット端末に「ペーパーライクフィルム」というものを貼り付けて使用する人が多い。
このフィルムは、文字通りガラスの液晶画面に紙のような細かな凹凸を再現するためのフィルムだ。
紙に鉛筆で絵を描くときのような摩擦感を再現することで、できる限りタブレット端末とタッチペンを紙と鉛筆に近づけようとしてくれる。
実際にこのフィルムを使ってみると、確かにガラス面でツルツル滑る画面に線を引くより圧倒的に描きやすくなる。
勿論それは紙と鉛筆の使用感と瓜二つではない。
けれどもさほど「ちょっと違う。紙と鉛筆の使用感はもっとこうだ」と文句を言う気にもならない。
なぜなら私たちはそれが「紙と鉛筆」ではなくて「タブレット端末とタッチペン」であることを理解しているからだ。
これは"紙と鉛筆風"だ。
偽物であることを前提に、この便利なタブレット端末とタッチペンが"紙と鉛筆風"になることがありがたい。
だから別にそれが偽物であることを強く指摘する必要がないのだ。
確かに少し紙っぽい、鉛筆っぽい。
この「〇〇っぽい」であったり「〇〇のような」という言葉は、それが〇〇ではない事を前提にして発せられている。
それが偽物である事を受け入れた上で居場所を与えるような肯定感がある。
高級フレンチっぽい。
そう言う時、それは高級フレンチではない。
言うなれば高級フレンチの偽物だ。
桃ような食感
それは桃ではない。偽桃だ。
それらに対して私が別に「高級フレンチってほどじゃないな」「桃とまではいかないな」と思ったとしてもそれはさして問題じゃない。
「まあ"っぽい"感じか」と納得させられてしまうのだ。
偽物は偽物である事を前提として存在していると、私たちはその存在になぜか少し寄り添ってしまう習性がある。

〇〇っぽい、〇〇のような、〇〇風味、〇〇味…etc.
私たちはそれらが本物ではないことを前提に、それを許容しようとする言葉を持っている。
この言葉によって受け入れさせられていると言ってもいいかもしれない。
例えば、こんな料理がある。
こんにゃくのステーキ
こんにゃくはステーキと同じ製法で作ったとてステーキにはなれないだろ。ステーキを舐めるな。
ステーキのことを「肉のステーキだな」とわざわざ思ったことはない。
ステーキと言ったらもう頭に浮かんでしまうのは十中八九肉なのだ。
こんがり焼いた厚切りの食材をステーキと呼ぶにしても、こんにゃくと肉では食材としてのパワーに差がありすぎる。
「俺はステーキだ!」と胸を張られると、こちらも「いや、全然違うやんか」と言いたくなってしまうものだ。
こういった時に使うべきなのが「〇〇風」だ。
こんにゃくのステーキ風
これなら誰も文句は言うまい。
ただの炙りこんにゃくをステーキと呼んだとしても、「風」と付くことで私たちはあくまで偽物として受け入れることができる。
頑張って背伸びをして、こんにゃくなりにステーキっぽくなれるように努めました!
そんな健気さを感じられる気がする。
そしてその健気さを汲んで、私たちはこんにゃくに「いけるいける!ステーキっぽいよ!」と肯定してやることができるのだ。

私たちはモノマネと言う芸についても偽物の許容をしている。
モノマネは文字通り、いかにそれを再現度高く真似るかで芸のクオリティが上がるはずだ。
しかし、阿部寛のモノマネが本当に阿部寛と完璧に瓜二つだった場合、沸き立つのは笑いじゃなくて恐怖だろう。
実際はそんなモノマネは無い。阿部寛は一人しか存在しない。
ならばモノマネというものは、阿部寛を到達点にしていないのでは無いだろうか。
阿部寛度を0〜10で測るとして、0が全く阿部寛を連想させない普通の人、10を阿部寛とする。
そうした時、阿部寛のモノマネとしての100点を目指すときに、阿部寛度10を目指してはいけない。
おそらく阿部寛度が6〜8くらいのモノマネが一番ちょうどいい。
私たちは阿部寛を完璧に再現してほしいだなんて元々思っていない。
だったら阿部寛を見るよ。阿部寛がいるんだもの。
私たちが阿部寛のモノマネに求めているのは、あくまで阿部寛の気配。
「阿部寛風味」なのだ。
阿部寛という原点から発生したモノマネは、『阿部寛'(あべひろしダッシュ)』を目指すのではない。
『阿部寛風〇〇』を目指すことになるのだ。
偽物とは、本物の紛い物とイコールにはならないことがある。
偽物が偽物として居場所を作る時、その偽物はその原点を空洞化し、ハリボテ的な外郭を保ったまま自立する。
こんな話をされてもイマイチ説得力が無いだろうか。
現実味が湧かないと言われるかもしれないが、あなたが求めているその『現実味』も、現実風味であって、現実とはまるで違うものかもしれない。
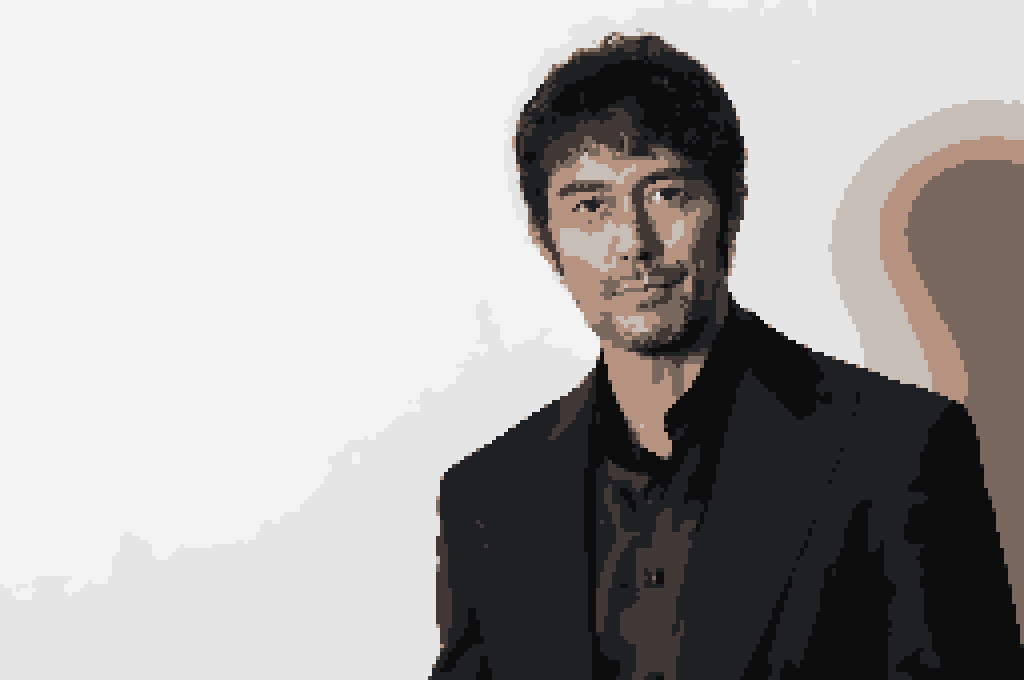
「現実味がある」もしくは「リアリティがある」と言った時、それが持っているのは本当に"現実らしさ"なのだろうか。
ここまで書いてきたように、コーラの味とコーラ味は少し違う。
高級フレンチっぽいものとは、高級フレンチではない。
では現実味があるものとは、より現実に近いということでは無いのかもしれない。
つまり、リアリティを感じることとは、それが現実であるかのように錯覚することではなくて、現実の気配を感じる事だ。
現実を模ろうとする創作物も、モノマネと同様に現実度を高めれば"現実味"は増していくだろう。
緻密に作り込んでいけばいくほど、それらの説得力がまるで現実のように伸びていく。
しかし、伸びていく枝は途中で突然現実から離れてしまうだろう。
思っているよりも現実というものは、曖昧でいい加減なものが多い。
小説や戯曲、映画などで描かれる「リアリティのある会話」というものは、実際現実的ではなかったりする。
それらは、鑑賞者に"物語られる範囲"が限定されている為、必要となる情報が明確になり、意味を持ち過ぎてしまうのだ。
例え無駄な会話というものさせても、それは演出意図に沿った「無駄なく無駄な会話をしている」という状態に過ぎない。
現実で行われる人と人との会話は、もっと前提とした情報や会話以前の文脈によって適当に端折られている。
映像やテキスト上で再現されたりするように、きちんと会話が成立していない事だって多い。
聞き取れなかったのに相槌を打ったり、知っているのに知らない程で一旦話を進めたりもする。
現実味を高めた創作物は、現実よりもきちんとしてしまう。
3DCGの表現でも、有名な「不気味の谷」と呼ばれる現象がある。
よりリアルな人間の顔に近づけようとしていくと、突然人間ではない不気味なものに見えてくるフェーズがあるという話だ。
モノマネの例のように、現実の再現度が0~10のパラメーターだとしても、創作された現実度は時に10を超え、その名の通り現実離れしてしまうのだ。
現実というものは、到達点というよりも、消失点のような性質を持っているのかもしれない。
私たちが求めているのは、現実を感じられるものではない。
添加物を徹底的に盛り込んだ、"現実的な味"だ。
私たちは偽物として振る舞う偽物を受け入れ、依然と本物を本物として崇めることができる。
だが同時に偽物を許容することで、その偽物をもう一つの本物として自立させることもできる。
本物の輪郭を少しだけ真似た偽物が、それぞれの認識の中で居場所を与えられ、まるで幽霊が受肉するかのように自立する。
もしかすると私たちの周りには、知らぬまに"偽物じゃなくなった者たち"が当然の顔をして歩きまわっているのかもしれない。
なおさら現実味が無いだろうか。